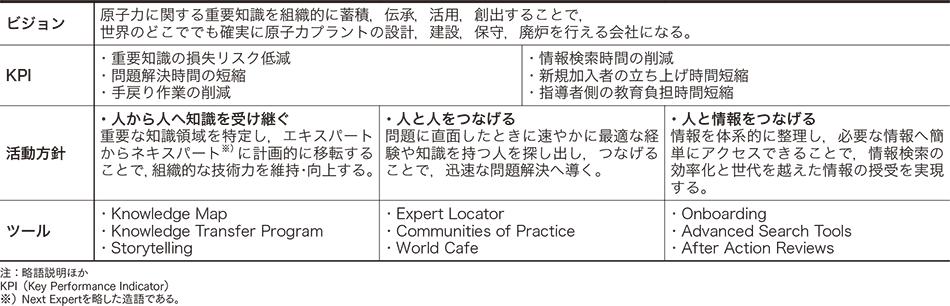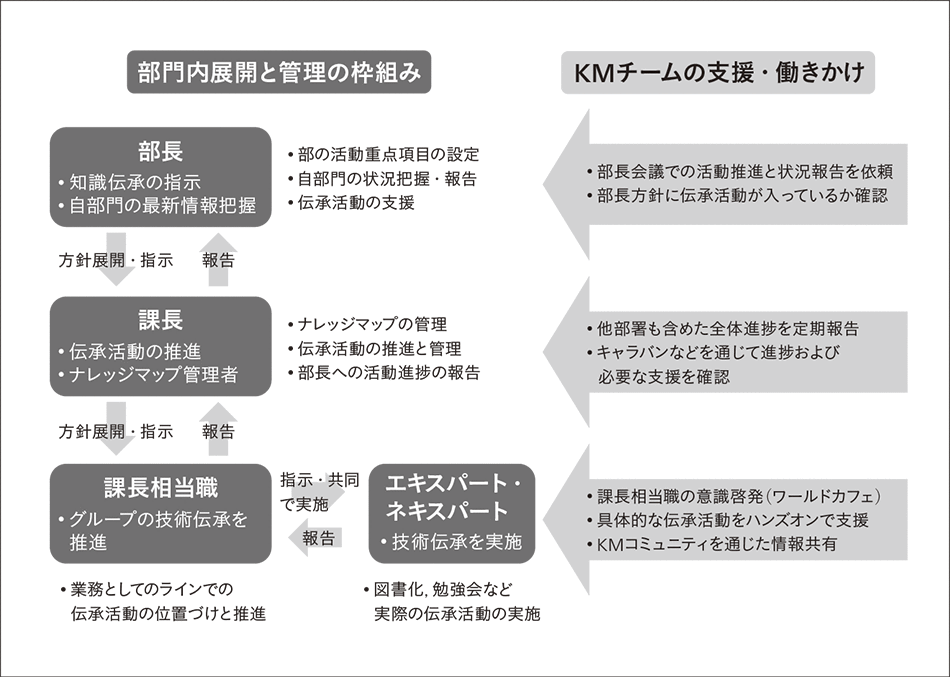原子力分野における日立の取り組み次世代に技術をつなぐ原子力分野でのナレッジマネジメント活動
ハイライト
現場を牽引してきた世代の退職や働き方改革への対応が迫られる中,知識や技術を組織的に管理し,次世代につなげることは多くの企業にとって重要な課題の一つと言われている。日立の原子力分野を担う日立GEニュークリア・エナジー株式会社でも,原子力技術の伝承は喫緊の課題である。そこで社外コンサルタントの協力の下,社内調査で課題を明確化し,国内外のナレッジマネジメント先進企業を直接訪問して,ベンチマーク結果を踏まえたナレッジマネジメントの導入を進めている。
本稿では,「人から人へ知識を受け継ぐ」,「人と人をつなげる」,「人と情報をつなげる」を活動方針として掲げ,2017年より取り組んできたナレッジマネジメントの活動内容および今後の展望を紹介する。
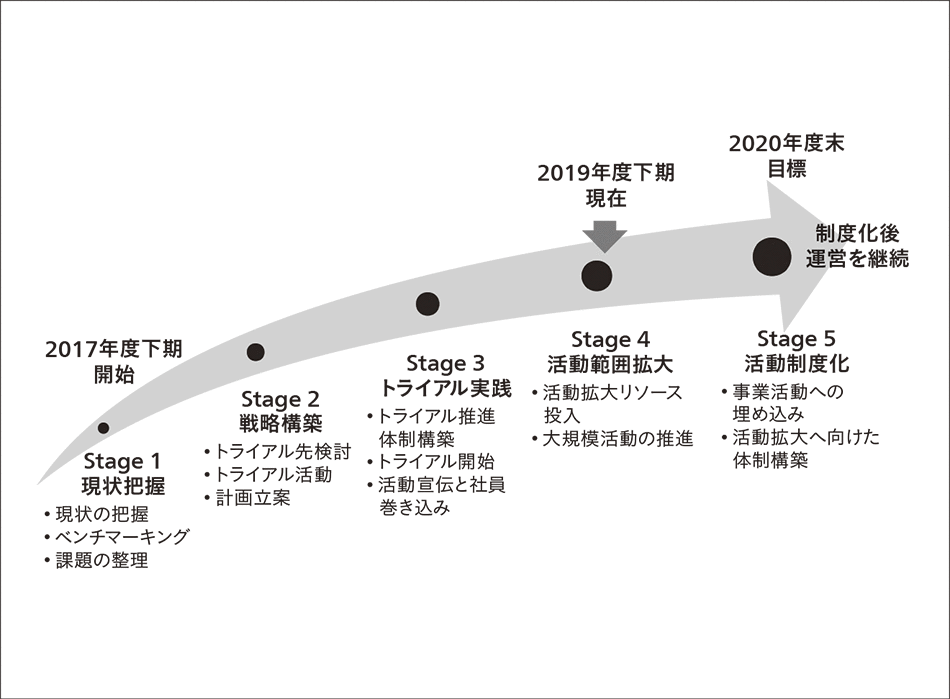
1. はじめに
日立GEニュークリア・エナジー株式会社(以下,「日立GE」と記す。)では,2017年に社内アンケート調査やヒアリングにより,社内業務改革の技術伝承に関わる中心的課題を洗い出した。その結果,一人ひとりの「暗黙知」としての技術は豊かである一方,そうした知を会社組織として体系的に活用できる状態になっていないことが分かった。これは,国立大学法人一橋大学の野中郁次郎名誉教授らが提唱したSECI(Socialization, Externalization, Combination, Internalization:共同化,表出化,連結化,内面化)モデルでいう所の「連結化」(形式知を組み合わせ,新たな形式知を作り出すプロセス)が全社的にあまり重要視されず,そのための時間も費やしていないということを意味していた1)。そのため,知の体系化と組織的な共有・活用の向上を日立GEのナレッジマネジメント(以下,「KM」と記す。)達成目標とした。
2. 国内外のKM先進企業からの学び
図1|KMの活動ロードマップ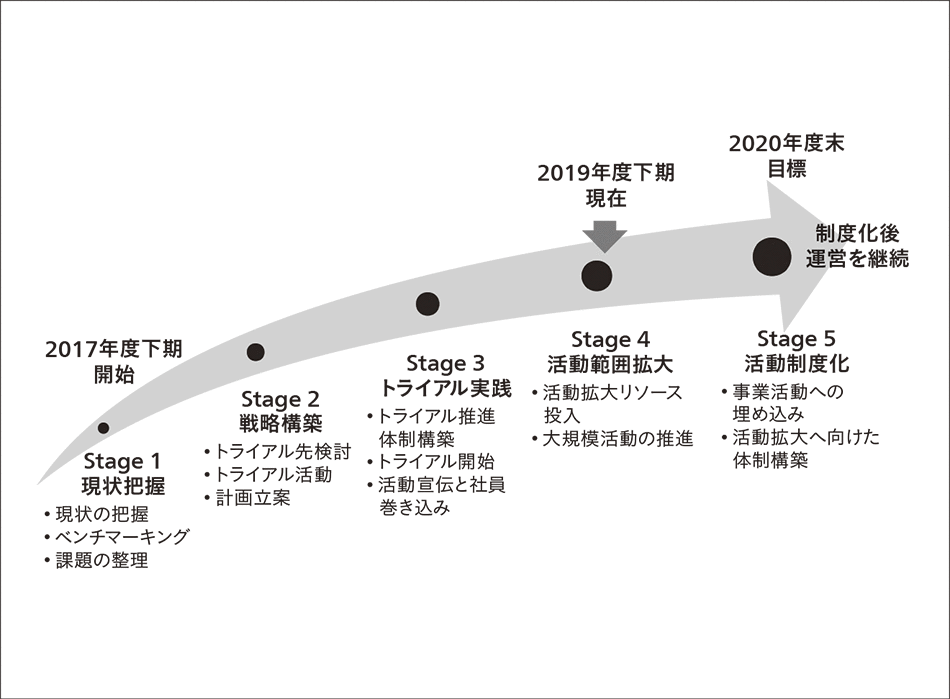 世界最大のナレッジマネジメント(KM:Knowledge Management)推進機関の一つであるAPQC(American Productivity & Quality Center)で用いられる成熟モデル(Maturity Model)をベースにしたものである。
世界最大のナレッジマネジメント(KM:Knowledge Management)推進機関の一つであるAPQC(American Productivity & Quality Center)で用いられる成熟モデル(Maturity Model)をベースにしたものである。
KMは2000年代前半にグローバルなブームとなったが,国内においては現在まで継続的に実践している企業の活動報告はほとんど見られない。一方,人財の流動化が当たり前であった多くの欧米企業では,技術をいかに組織内に留めるかは長年の課題であり,その手段としてのKMは経営活動の一部として定着していた2)。
そのため,KMの推進にあたり,米国企業のベンチマーキングを実施した。ベンチマーキング先は,米国最大のKM推進機関であるAPQC(American Productivity & Quality Center:米国生産性品質センター)およびその協賛企業とした。
そこから学んだKM成功のカギは,経営課題とKM戦略をリンクさせること,推進ガバナンスを構築すること,活動ロードマップを定め段階的に推進することの三つであった。そこで,日立GEのKMロードマップでは,図1に示すように,Stage 1で現状把握,Stage 2で戦略構築,Stage 3でトライアル実践,Stage 4で活動範囲拡大(全社展開),Stage 5で活動制度化を段階的に推進することとした。
日立GEのKMは,Stage 1をクリアした段階で始動し,次にStage 2の戦略構築として活動方針を策定した。会社のビジョンおよびKPI(Key Performance Indicator)を達成するためのKMのビジョンや活動方針「人から人へ知識を受け継ぐ」,「人と人をつなげる」,「人と情報をつなげる」を定めるとともに,具体的な活動内容を設計した(表1参照)。次章では,日立GEが特に注力した,人から人へ知識を受け継ぐためのナレッジマップの作成推進について述べる。
3. KMの活動内容
KM推進に重要なことは,組織の重要な知識(技術)を洗い出し,体系的に管理することである。日立GEでは,Stage 3の中心施策として,海外の多くの企業でも取り組まれているナレッジマップの作成を設計部門で推進した。
3.1 ナレッジマップの作成方法の検討
ナレッジマップの作成方法やまとめ方は企業によって異なるため,作成にあたっては自社にとって最適な手法を模索する必要があった。日立GEのナレッジマップの基本的な構成要素は,技術領域の洗い出し,保有者の特定および優先度の決定,伝承方法および期限の設定である。日立GEのナレッジマップ構成例を図2に示す。なお,エキスパートの技術を引き継ぐべきネキスパート※)の明確化とその育成は,ベンチマーキング先の米国企業の多くで実際に用いられていたKM手法の一つである。
図2|原子力発電所のナレッジマップの例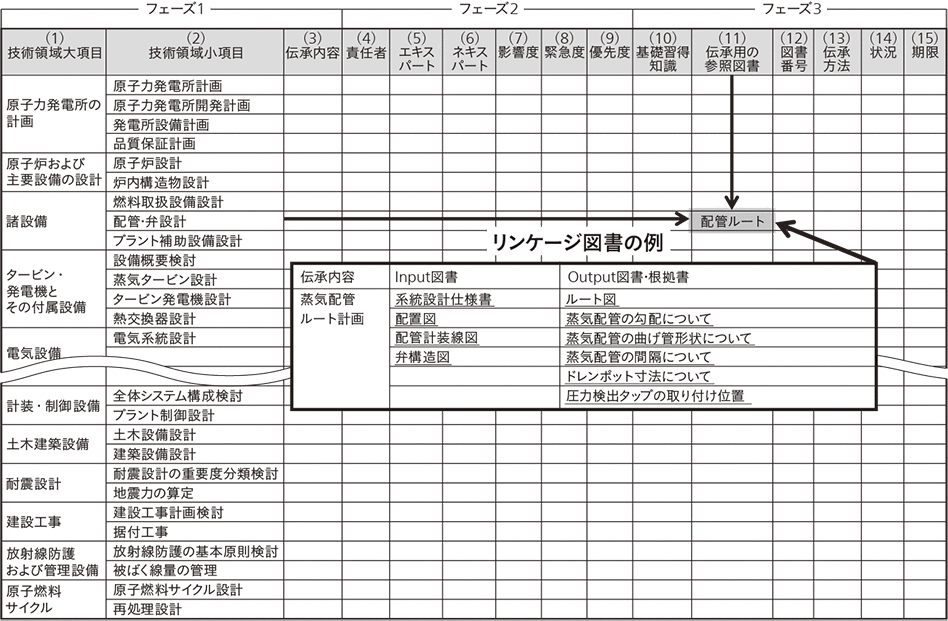 ナレッジマップでは,技術領域ごとに保有する知識を体系的に洗い出し,技術伝承の優先度を可視化することが可能である。一つの伝承内容と複数のInput・Output図書をひも付ける場合,リンケージ図書と呼ばれる図書一覧とリンク先を示す図書を作成する。
ナレッジマップでは,技術領域ごとに保有する知識を体系的に洗い出し,技術伝承の優先度を可視化することが可能である。一つの伝承内容と複数のInput・Output図書をひも付ける場合,リンケージ図書と呼ばれる図書一覧とリンク先を示す図書を作成する。
- ※)
- Next Expertを略した造語である。
3.2 ナレッジマップの作成手順および伝承活動の実施
ナレッジマップは,課内に複数存在する5~10数名のグループ単位で作成することとした。洗い出しの方法としては,まず課長にアサインされたネキスパート(35歳前後が中心)がドラフト版を作成する。次に,チーフエンジニアを中心としたエキスパートおよびアドバイザーと共に簡単なワークショップを開催し,洗い出しの項目の確認・修正を行う。このワークショップは,ネキスパートにとってはエキスパートの保有する知識を学ぶ機会として,エキスパートにとってはネキスパートの悩みや知識不足の領域に気付く機会としても機能した。ナレッジマップの項目を1回のワークショップで埋めることは困難なため,以下の三つのフェーズで作成を推進した。
フェーズ1:技術領域・伝承内容の洗い出し
技術領域(大・小項目)および伝承内容[図2列(1)~(3)]を洗い出す。
フェーズ2:責任者,エキスパート,ネキスパートの設定および,優先度の決定
各伝承内容のエキスパート,ネキスパート,影響度および緊急度,優先度[図2列(4)~(9)]を設定する。
- 影響度は,その伝承内容の重要性を表し,自社独自の固有技術なら点数を高く,教科書に載っているような周知の技術なら点数を低く設定する。
- 緊急度は,その伝承内容の緊急度合いを表し,1人なら点数を高くし,55歳以上は何人いても1人としてカウントするなど,技術を保有するエキスパートの人数で機械的に算出する。
- 優先度は影響度と緊急度を掛けた数値であり,伝承内容の優先順位を表す。
- 各伝承内容の責任者は,ナレッジマップの責任者である課長とする。
このフェーズ2までをナレッジマップの作成と位置付け,活動を推進した。
フェーズ3:技術伝承活動の実施
伝承危機にある技術が可視化された後は,各グループで技術伝承活動を進める[図2列(10)~(15)]。
- 優先度が高い(重要度・緊急度が共に高い)技術に関して,伝承方法と期限を設定する。
- 技術によって最適な伝承方法は異なるため,資料の作成・整理,勉強会実施,模擬訓練や現場実習など実態に合った伝承活動を設定する。
- 可能な限り暗黙知を形式知化するために,資料の作成・整理(エキスパートの頭の中の知識を引き出して資料にすること,エキスパートが保有する分散した資料の整理など)を基本の伝承方法とする。
- Input図書(他部署からの情報や規格・基準などから得られる図書)およびOutput図書・根拠書(自部署で作成する図書であり,内部資料として使用するものも含める)などを一覧にまとめ,それぞれの図書の格納リンク先もひも付けておくことで,図書を素早く確認することが可能なリンケージ図書を作成する。
4. 活動の推進により見えてきた課題
ベンチマーキングでは,KMの遂行にガバナンス,とりわけ骨太な推進体制の構築が重要であることを学んだ。そこで,スポンサーに会社のトップを,アドバイザーに技師長を,KM推進者に各技術領域の設計者をそれぞれ配置することで,推進ガバナンスの基本骨格を構成した。組織全体で活動するためには,トップダウンだけでなく,従業員がその重要性を認識することが不可欠であり,幅広くKM活動を浸透させる必要があった。
4.1 ナレッジマップ作成の阻害要因
当初はトップダウンにより,設計全部署のナレッジマップのフェーズ2[図2列(9)まで]を半年間で完了する予定であった。しかし,半年経過後の作成完了部署は,予定の半分にも満たなかった。各課の実態を確認するためにヒアリングを行ったところ,「顧客対応業務が最優先」という考えが,KMの優先順位を上げづらくしていることが分かった。そのため,各従業員がKMの重要性を認識し,業務の一つとして本活動に従事できるようにすることが不可欠と判明した。
4.2 ナレッジマップ作成推進における対策例
前節に示したようなKM推進上の悩みは,部長,課長,課長相当職,エキスパートおよびネキスパートといった階層により異なるため,各階層に適したプロモーションが必要であり,基本スキームを設定した(図3参照)。
- 部長に対しては,部の活動方針へ技術伝承活動を入れ込むことと,毎月実施する部長連絡会議での定期的な推進報告を依頼した。
- 課長に対しては,他部署を含めた社内全体進捗の定期報告と,期ごとに実施するヒアリングを通じた進捗確認および必要な支援の確認を実施した。
- 課長相当職に対しては,人数規模も大きく,かつ具体的な技術伝承活動推進が必要であるため,技術伝承活動への意識啓発と,各部署の技術伝承活動の取り組みや悩みを共有する施策としてワールドカフェを実施した。ワールドカフェとは,お互いの考え方,テーマに関する取り組みや悩みを話しやすい雰囲気の中で共有する大規模な対話集会であり,初回は200名強で実施した。
- エキスパートとネキスパートに対しては,ナレッジマップ作成ワークショップのファシリテートなどを通じたハンズオン支援を実施した。さらに,各課の代表ネキスパートには,ナレッジ連絡会を通じて,各部署で実施している伝承活動のベストプラクティスや,伝承活動を推進するうえでの課題およびその対策の共有を実施した。
以上のプロモーションは,技術伝承活動を組織内へ定着させるうえで非常に有効だったと考える。
4.3 KM活動の継続に向けて
これまでの活動を通じて,KMの重要性についての従業員の理解が深まったと考えている。また,ナレッジマップを作成することにより,現在までの知識・技術を洗い出し,体系的に管理することができるようになった。一方で,これから生まれる技術に対してもアプローチする必要がある。これについては,各課・各グループの業務プロセスに,技術伝承を埋め込む必要があり,今後のKM活動の課題と考えている。
5. おわりに
技術伝承は終わりのない活動と言われている。原子力分野においては,発電所の建設から廃炉まで100年に及ぶ長期間の技術の維持が求められる。一度失われてしまった技術を取り戻すには相当の時間を要するため,組織としてのKMの一層の推進が求められている。日立GEのKM活動はこれまで設計部門を中心としていたが,今後は,プロジェクト部門,品証部門および現場にもロードマップStage 4に定める活動範囲の拡大を予定している。また,Stage 5の活動制度化についても,ナレッジマップと人事情報の連携のシステム化など現在推進している活動の高度化や,事業活動への埋め込みなど,継続的に活動を拡大していく予定である。
謝辞
本稿で述べたKMの推進活動においては,富士ゼロックス株式会社のコンサルティングチームに協力を頂いた。深く感謝の意を表する次第である。
参考文献など
- 1)
- 野中郁次郎,外:知識経営のすすめ,筑摩書房(1999.12)
- 2)
- ドロシー・レナード,外:〈新装版〉「経験知」を伝える技術,ダイヤモンド社(2013.9)