Digital Solutions for a Better Future Society より良い未来社会を拓くデジタルソリューション
2020 Vol.102 No.3

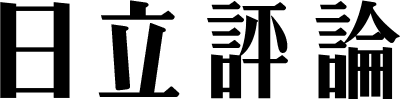

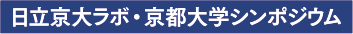

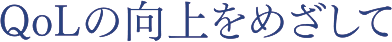
生物界にはハチやアリのように集団において各自の役割が規定されている「社会性昆虫」と呼ばれる種が存在する。またゴリラなどでは立場の強い者同士の争いを,弱い立場の者が対面姿勢でコミュニケーションを図り仲裁するといった生態も観察されている。さらに我々人間はなぜ国家のような大規模かつ複雑な社会を構成し,お互いに協力し合うことができるのか。そして,生物が持つ多様な「社会性」からQoL(Quality of Life)を向上させるために何を学ぶことができるのか――。
2020年2月,「生物の社会性に学ぶ新たな社会システムの可能性」と題して東京都内で開催された日立京大ラボ・京都大学シンポジウムでは,第一部でイヌやイルカ,アリといった身近な「生物の社会性」について,第二部で人間の社会的行動やコミュニケーションといった「人の社会性」について,それぞれ気鋭の研究者が最新の研究成果を発表し,300名以上の聴衆を前に熱のこもった討論を展開した。

シンポジウムの冒頭,京都大学産官学連携本部副本部長の木村俊作氏が開会挨拶に立ち,日立京大ラボ設立の経緯と成果の一つであるAIシミュレーションによる2050年のQoL予測について紹介し,「QoLには健康,環境,経済などさまざまな切り口があるが,QoLは社会システムにおける社会的価値が決まっていないと決められない。生物の社会を見るとそれらは優れたリーダーによるトップダウンではなく,ボトムアップあるいは自己自己組織的・創発的なプロセスを通して決まるものであると気づく。生物の社会を学ぶことで私たちの社会や振る舞いを見直し,サステナブルな社会につながることを心から願う」と期待を述べた。
続いて日立製作所執行役常務CTO兼研究開発グループ長の鈴木教洋は,日立京大ラボのAI開発に言及しながら,「AIは人間を模擬するものだが,人類の歴史は20万年,生物の歴史は40億年。長大な歴史で生物がどのような社会性を獲得してきたのか,それを将来の社会システム実現に向けた議論の中で役立てたい」と抱負を語った。
さらに「勉強家」の肩書きを持ち,京都精華大学人文学部特任講師を務める兼松佳宏氏がシンポジウムの座長として登壇し,「自分はこれからの社会の作り方に興味を抱いてきた。今日は来場者の皆さんを代表し,勉強家として講演者の皆さんに質問し議論を深めていきたい」と会場を盛り立てた。




村山氏の専門は野生動物分子生態学。行動観察に加えて,遺伝子の側面からも動物の生態を研究している。ここでは,私たちに最も身近なペット・家畜であるイヌの社会性とともに,性格や「こころ」に迫る研究を紹介していただいた。
遺伝子の本体であるDNAは,動植物をはじめすべての生物に共通するものである。同時にチンパンジーとヒトでは1.3%,ヒトの間でも0.1%以上の違いがある。少ないようだが,3億塩基分の300万塩基であるから無視できない。一人ひとりの遺伝子の違いはDNAを構成する四つの塩基配列(ATGC)によるもので,その配列の違いで決定されるたんぱく質の構造が異なる。遺伝子の違いを解析することで,種や個体それぞれの特徴や個性を把握・理解できる。
動物の排泄物や唾液,羽などから採取したDNAから,種や亜種,地域集団といった大きな単位の識別だけでなく,集団の中の多様性の度合い,血縁関係,性別,腸内細菌などを個体単位で識別することが可能となっている。また近年,ヒトの行動や性格に関係する,主に神経伝達に関わる遺伝子についての研究成果が報告された。例えば,ドーパミンの受容体の繰り返し配列が長い人は新奇性を追求する志向が強く,セロトニンを回収するトランスポーター遺伝子の長さが短い人ほど不安を感じやすい。我々はこれを動物にも応用したいと考え,イヌの研究を行っている。
研究の結果,D4遺伝子というドーパミン受容体の長さが短い犬ほど社交性が高く,長い犬ほど攻撃性が高いことが分かった。これを品種ごとに照らし合わせてみると,イヌの祖先であるオオカミは長いタイプのD4遺伝子を多く持ち,アジア在来犬,番犬・猟犬,伴侶犬・回収犬など,新しい品種になるほど長いタイプを持つ割合が低かった。ヒトとイヌの長い歴史の中で,互いに共存できる社交性の高い種が選抜されてきたことの反映と考えられる。また麻薬探知犬についても,社会性に関わる遺伝子とされるオキシトシン受容体の1塩基の配列差によって合格率に有意な差が見られるなど,イヌでも遺伝子と性格や行動に強い関連があることが判明している。性格の違いは健康や寿命にも関わると言われるが,遺伝子型によって個体の性格や「こころ」が分かれば,それぞれに適した飼育方法の目安になるだろう。今後も私たちに身近なイヌをはじめとした伴侶動物や,動物園で飼育されている野生動物のストレス予防や飼育環境の改善,繁殖への活用などをめざして研究を進めていきたい。
長い間パートナーシップを築いてきたイヌとヒトだが,互いに見つめ合うことで愛情ホルモンと呼ばれるオキシトシンが高まるなど,種を越えて互いに影響を与え合っていることも分かっている。このように人間と他の動物の違いに着目するだけでなく,私たちも動物の一員であり自然や生態系の一部として存在していることを忘れてはならない。一方で,生物の社会で制御できていない平和や福祉を扱えるのも人間であり,私たちはそれも自覚し大切にしていくべきと思う。

酒井氏の専門は動物行動学。伊豆諸島の御蔵島で10年以上にわたり野生のミナミハンドウイルカの社会行動を観察している。ここでは,水中で暮らすイルカの長期観察を通して初めて明らかとなった社会性と私たち人間社会との共通点についてお話しいただいた。
イルカはクジラ偶蹄目に属する哺乳類で,約76種が確認されている。単独または母子のペアで暮らすスナメリ,母系の群れで暮らすマッコウクジラ,群れのメンバーが日々変わる離合集散型のハンドウイルカなど,その社会性は種によってさまざまだ。中でも我々が研究対象とするハンドウイルカの社会は特に複雑で,オス同士は一次同盟,二次同盟といったように入れ子状の同盟関係を築き,メスをめぐる争いの際に協力する。一方で,多くのオス同士が参加するスーパーアライアンスという同盟を組むこともある。とりわけ仲の良い個体関係もある中で多くの個体と付き合い,群れのメンバーは日々入れ替わる。
イルカは独自のコミュニケーション方法をいくつも持ち,それによって複雑な社会関係を維持する。例えば音による長距離コミュニケーションでは,名前と同じく個体固有の抑揚を持つホイッスルという音を用いて,互いに数百メートル離れた仲間たちと鳴き交わし,音を真似ることによって群れを維持する。ホイッスルは最大2.5 km程度まで届く。他にも胸びれで相手の体をこするラビングという触れ合い行動や,ダンスや楽器演奏と同じように複数の個体が「呼吸」を合わせて並んで泳ぐコミュニケーションなどがある。後者は母子・メス同士・オス同士など,関係性や親密度によって相手との距離が異なることもヒトと共通している。
御蔵島のイルカたちを観察して新たに分かったのは,イルカにも養子取りの行動があることだ。血縁関係や社会関係もなく子育ての経験もないメスイルカが,母親を亡くした子イルカの里親になっていて,母子のようなラビングを行い,母乳を与える様子も確認された。このようにイルカは,ヒトと同じく他個体(他者)を助ける向社会的行動も行うのである。
ヒトとイルカは約1億年前に分岐したまったく異なる系統の哺乳類である。海と陸で異なる環境に生息するが,両者とも大きな脳を持ち,複雑な社会と多様なコミュニケーション方法,向社会的行動といった相似する形質を進化させてきた。これを生物学では「収斂」と呼ぶ。
現在,インターネットやSNSなどの普及で私たちの言葉や情報を通してコミュニケートできる距離は飛躍的に広がった。一方で直接お互いに顔を合わせるコミュニケーションは希薄化している。イルカが進化とともに発達させてきた社会性を知ると,持続可能で人間らしい豊かな社会を築いていくためには,便利な長距離コミュニケーションだけではなく,互いに触れ合い呼吸を合わせて「場」を共有するようなコミュニケーションも重要だと感じられる。

土畑氏の専門は進化生態学。アリなどの「社会性昆虫」を対象に,振る舞いや暮らしぶりの多様性やそれをもたらす遺伝的多様性がどのように保たれるかを研究している。ここでは,人間社会を考えるうえでも身につまされるようなアリ社会の驚くべき現象についてご紹介いただいた。
DNAの遺伝情報には,まれにコピーエラー=「突然変異」が起こる。偶発的な変異で発生したものが環境に適応し,自然に増えていくプロセスが「自然選択」である。突然変異は生物にとっての最適値を「探索」し,自然選択は見つけた値に対し「最適化」していくプロセスとも言える。生物の表現型が多様なのはそれだけ環境が多様であるということ。多様な環境下では集団「間」の多様性は担保されるが,単純な自然選択だけが働けば,むしろ一つの環境では適応した生物だけが増え,集団「内」の遺伝的多様性は減ることになるはずだ。だが現実はそう単純ではない。
我々が研究するアミメアリには,子どもを産み自分で育てる協力系統の「働くアリ」と,子どもを産んでも自分で育てない非協力系統の「働かないアリ」の二種がいて同じ巣の中で暮らしている。不条理なことに働かないアリの方が,体が大きく卵をたくさん産めるので自然に増加する。しかし自分で子育てできないため,シミュレーション計算だとその群れは10世代(10年)で滅ぶ。しかし,働かないアリは現に存在し,何と9200年も前からこの二種が共存していることが判明した。この不思議な現象のからくりは,稀に起こる働かないアリの「引っ越し」にあった。約2万匹が住む群れの中で,1世代につき1匹の働かないアリが別の巣へ移動することによって命をつないでいたのだ。「2万匹でたった1匹」が両種が共に滅亡しない絶妙なバランスであり,多すぎても少なすぎても共存し続けることができない。
これは自然選択理論の「負の頻度依存選択」と呼ばれるメカニズムによるもので,集団の中で有利だった種の割合が増えすぎると逆に不利に変わることで全体のバランスがとれる。その結果,群れの中で両種が生存し,多様性が保たれるという仕組みだ。自然淘汰が長期にわたる均質化を防ぐ方向に働くとも考えられるが,人間社会と照らし合わせてみると,どう捉えられるか。
生物の生態を観察・研究し,自然を理解することは,あらゆる生物に共通するDNAの「物質レベル」と,自然の力学や進化的背景といった「システムレベル」の二つの側面から人間理解を促すだろう。多様な生物の社会を,もしかしたらあり得たもう一つの人間社会として捉え,私たち自身のあり方を相対化し問い直す契機としていきたい。


高岸氏は,人間の「向社会的行動」を支える脳と遺伝子の働きを探る研究に取り組んでいる。ここでは,人間の本性とも言える向社会性はいかに形成されたのか,真のQoLを考え直す手掛かりについても併せてお話しいただいた。
なぜ人間は,見ず知らずの人を助けるのか。ホームに落ちそうな人を助け,震災復興のために募金をする。このように自らお金や時間などのコストを支払い,他者の利益のために行動することを「向社会的行動」と呼ぶ。他の動物ではほとんど見られない不思議な行動で,人間の本性を考えるうえでも極めて興味深い。
まず我々は,自然選択理論が示すように生物の形質は環境によって決定されるだけでなく,個体が積極的に環境に働きかけ,その環境に適応する形質に進化させてきたと考える。これを「ニッチ構築」,さらにそれを応用したものを「社会的ニッチ構築」と呼ぶ。一説には,人間は今日に至る進化の過程のほぼすべてを100名ほどの集団で生活してきたと考えられている。閉じられた集団内では,相互監視と個人に関する情報を広める噂話や評判が発達し,個人が生存するうえで裏切りや非協力的な行動はむしろ不利に働いた。つまり,集団生活の中で向社会的行動が有利となる環境が人工的に作り出された結果,それに適応する心の性質を進化させたのではないか。この仮説が正しければ,人間は「デフォルト」の状態で利他的であるはずだと考えられる。
我々は玉川大学周辺の住民たちの協力による大規模調査(2012年から約500人が参加)において,さまざまな経済ゲームを用い,複数主体が意思決定に関わる場面で個人がどのような行動を選択するかを測定・分析した。その結果は上記の仮説を支持した。集団のために協力する人ほど意思決定の時間は早く,逆に時間を掛けると非協力的になる。熟慮的意思決定で使う前頭皮質の厚さの計測や脳の活動量を可視化する実験などからも,人の向社会的行動は「自動化」されており,むしろ脳を積極的に働かせないと非協力的行動は行えないことも分かってきた。
ただし個人差があり,閉じられた集団に属す人とそうでない人ではデフォルトの向社会性の発達に差異があると推測される。これは置かれた環境によって心の性質が異なってくる可能性を示すが,人は自ら生きる環境を選び,個体自ら働きかけて環境を構築することもできる。人間の心は,個体と環境のダイナミックな相互作用によって生まれると言えるだろう。QoLの要因は各人の環境とそれに伴う心の性質によって変わるが,社会制度のあり方もどのような人間モデルを想定するかで異なってくる。より善い社会の実現にはこうした人間の本性に対する理解を深めていくことが欠かせない。

高田氏は人類学が専門で,南部アフリカのサン族を主な対象に,フィールドワークを通して乳幼児と養育者の「相互行為」を研究している。ここでは,両者のコミュニケーションと発達経路をめぐる考察からQoLをどのように捉えるべきかをお話しいただいた。
「相互行為」とはコミュニケーションよりも広い意味の概念だ。乳幼児と養育者の相互行為が言語の使用など,さまざまな様態のコミュニケーションに拡張され,人間の社会システムが形成されると考えられる。最も基本的かつ普遍的だと考えられてきた相互行為は赤ちゃんの吸てつ(口に入ってきたものを強く吸う生得的行動)と養育者によるジグリングで,吸てつが止むタイミングで養育者が赤ちゃんの体を揺することで授乳時間が伸びていく。他にも初期音声や音楽性を利用するもの,モノや言語を介しての関わりなど,発達段階に応じた特徴がある。人間の社会的行動は相互行為に始まる模倣学習,幼稚園での教示学習,小学校での共同学習といった文化学習を通じて集団内に広がり,それが次世代に継承されていったと考えられる。
しかし我々がフィールド研究を行うサン族では,普遍的とされてきた吸てつとジグリングの行為が見られず,授乳は頻繁で短い。これは私たちが暮らす近代社会とは異なり,養育者(母親)はいつでもどこでも授乳ができること,授乳中もマルチタスキングであることなどが要因に挙げられる。他方,歩行反射を利用してあやすことで歩行行動が生後2,3か月になっても消失せず,独り歩きが早く達成されるといった特徴もある。したがって,養育者が利用する乳児の生得的パターンは文化によって多様であり,その養育行動の違いによって子どもの発達経路も異なると考えられる。従来はこのような地域固有の文化的多様性は十分に考慮されず,欧米型の近代社会モデルに基づき文化学習も捉えられていたが,人間社会の実態を踏まえれば,現在とは異なる発達経路や文化学習の可能性もあるだろう。
将来社会のQoLを考えるうえでも,人間社会の多様性やそれが辿ったダイナミックな変化プロセスを理解することは有益である。人間社会は,狩猟採集社会から,農耕社会,産業社会,情報化社会へと変化するにつれて,より大きな集団が共同できるように移り変わってきた。それに伴って道具,記録媒体なども変化してきた。その過程は,人間の思考と行為の外在化が進んできたものと考えられ,AIはその延長にある産物であろう。それに合わせて人間の思考のスタイルも変わり,内面的な変化が起きていると思われるが,これについての研究はいまだにあまり進んでいない。ここでは,そうした社会の仕組みや道具の総体を「外的なエコロジー」,人間の心や思考の総体を「内的なエコロジー」と考え,両者の調和としてQoLを捉え直すことを提案したい。両者はいずれも重要であり,相互に増強可能であると考えられる。本発表で紹介したような相互行為,すなわちさまざまな社会的状況での「意味」のやりとりの丹念な分析を通じて,その関係を明らかにしていきたい。


小林氏の専門は建築学だが,世界中で地域に根ざした「風土建築」の再建プロジェクトに携わる。その中で見えてきた風土建築と地域固有の環境や文化との有機的関係から,QoLを考えるうえでも重要なローカリティの価値についてお話しいただいた。
「風土」とは,ある地域の気候や地味,地質,景観などの総称で,かつて哲学者の和辻哲郎は風土と人間形成の関係を説いた。そして,「風土建築」とは,地域環境のさまざまな条件や制約の中で形成された地域に根ざした建築をさす。しかし,市場経済の浸透や価値観の変容などグローバル化の波は世界中の辺境の地にも及んでおり,建築資材となる有用木材の減少や伐採制限,トタンやコンクリートなどの新建材普及,伝統建築を貶める風潮などによって消滅の危機にあるのが実態だ。我々は,ベトナムやタイ,フィジーなど各地で風土建築の再建に携わる中で,現代社会における風土建築の意味と発展的継承のあり方を考えてきた。例えば,ベトナム少数民族カトゥ族の再建プロジェクトでは,村人全員が資材集めと建設に協力し,ベトナム戦争後,初めて自らの伝統的集会施設が「我々の家」として建ち上がった。そこでは若者達が伝統舞踊や織物を始め,またWi-Fiカフェや宿泊施設として利用されるなど,現代の生きた建築として集落生活の中で生かされている。
再建プロジェクトを通して強く認識したのは,風土建築は「伝承技術(知的資源)」,「共同労働(人的資源)」,「在地資材(物的資源)」の三つの地域資源からできているということだ。
森の資源がコミュニティに恵みをもたらし,コミュニティの世代間伝承が建設機会に在来の知恵や技術を伝え,その知恵や技術が森の資源の循環的活用を促すように,これらは相互に連環し,地域固有の環境や文化を豊かに機能させる。しばしば,外部の支援組織によって伝統建築の再現が行われるが,在地資材ではなく「新建材」,伝承技術ではなく「産業技術」,共同労働ではなく「請負施工」によって建設されることがある。これらは外部資源に依存している点で,形態が類していてもその成り立ちや意味合いはまったく異なる。
これらの経験から,現代社会においてもう一度,地域固有の智恵や技術,自然環境やコミュニティのあり方に着目し,ローカリティの再評価や価値の再定義を行う必要性を感じる。その試みは,我々の拡大成長型社会を転換し,将来の新たな社会形成につながっていく。今,日本で社会問題となっている放置竹林の竹材を有効利用し,簡易な技術でセルフビルドできる竹構造農業用ハウスの開発と普及をめざすプロジェクト(バンブーグリーンハウスプロジェクト)に研究室で取り組んでいる。これまで30棟ほどさまざまな場所で地域の人々の手によって造られており,これも風土建築の経験から発想し実践しているものである。地域に根ざす建築の「再生」から「創生」へつながる活動を今後も進めていく。

以上のプログラムを終えて,閉会の挨拶に日立製作所基礎研究センタ長の西村信治が登壇し,「生物やQoLについて新たな捉え方や提案を頂き,考えさせられることの多い一日となった。今後,この学びをどのように社会に実装していくか,京都大学,日立京大ラボ,そして皆様と力を合わせて議論し進めていきたい」と締めくくった。