日立-産総研サーキュラーエコノミー連携研究ラボ 第2回オープンフォーラムCE社会のありたき将来と実現に向けた具体的アプローチ
ハイライト
従来の「線形経済」から「循環経済」への移行に向けた取り組みが国内外で広がりを見せる中,日立製作所と産業技術総合研究所の連携により,2022年10月に発足した日立-産総研サーキュラーエコノミー連携研究ラボでは,「循環経済社会のグランドデザインの策定」をはじめとした三つの研究テーマを掲げ,あるべき循環経済社会像やそこで必要とされるルール・ソリューションについての検討を進めている。
循環経済社会の将来の姿とそこに至る道のりにおける技術的,制度的課題を抽出し,関係者と問題意識を共有した2024年の第1回に続き,2025年2月に開催された第2回オープンフォーラムでは,CE社会における「ありたき将来」と,そこに至るための技術とルールに関する同ラボの検討結果が報告された。また,外部の有識者を交えたパネルディスカッションを通じて,CEの実現に向けた要件と,人と企業の行動変容を促すルールのあり方についても議論が交わされた。

 [司会進行]
[司会進行]
寺田 尚平
産業技術総合研究所 日立-産総研サーキュラーエコノミー連携研究ラボ 副ラボ長
暮らしやビジネスに欠かすことのできない資源の枯渇が懸念される中,大量生産・大量消費を前提とした「線形経済」から,リサイクル,リマニュファクチャリングなどを通じて資源を循環的に利用する「循環経済(CE:Circular Economy)」への移行をめざす取り組みが世界的に広がりつつある。こうした中,CE社会の実現を研究テーマに掲げる日立-産総研サーキュラーエコノミー連携研究ラボ(以下,「日立-産総研CEラボ」と記す。)の第2回オープンフォーラム「CE社会のありたき将来と実現に向けた具体的アプローチ」が2025年2月に開催された。司会進行は,日立-産総研CEラボ 副ラボ長の寺田 尚平が務めた。
1. 開会挨拶
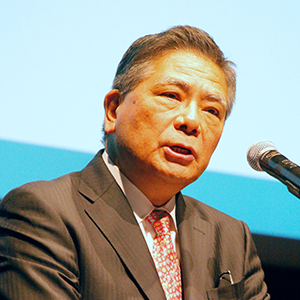 石村 和彦
石村 和彦
産業技術総合研究所 理事長 兼 最高執行責任者
 小島 啓二
小島 啓二
日立製作所 執行役社長 兼 CEO
フォーラムの冒頭では国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下,「産総研」と記す。)の石村 和彦理事長が開会の挨拶に立ち,前回のオープンフォーラムからの約1年間におけるCEを取り巻く国内外の動向に触れたうえで,「CEは一企業,そして一研究機関が単独で実現できるものではありません。CEを現実のものとするためには,多様な企業や研究・教育機関,投資家,政府など,立場の異なる組織が相互に連携しながらイノベーションを創出するエコシステムの形成が重要です。」と述べ,本フォーラムのプログラムを概説するとともに,参加者・登壇者への謝辞を寄せた。
また,日立製作所 執行役社長 兼 CEOの小島 啓二は,CE実現に向けたオープンソース活用の重要性と本フォーラムの意義について次のように述べた。「循環型社会の構築に向けては,オープンソースコミュニティのように多様なステークホルダーが技術や知見をオープンに共有することが重要になってきます。既にあるものを再利用することは資源やエネルギーをむだなく使い,よりよいものを効率的に生み出すことにつながります。本日のオープンフォーラムでの議論が,さまざまな知恵や考え方の循環につながることを期待しています。」
2. 特別講演
CEを取り巻く標準化動向と日本のめざす方向性
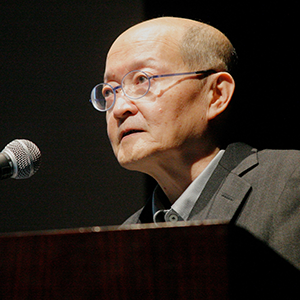 市川 芳明
市川 芳明
多摩大学 客員教授,ISO/TC323/WG2 元国際主査
続いて,多摩大学 客員教授でISO/TC323/WG2 元国際主査の市川 芳明氏が登壇し,国内外におけるCE関連の国際標準化の状況と今後の展望,日本の戦略に関する特別講演を行った。
市川教授はまず,CEに関連するISO(International Organization for Standardization)で唯一の国際標準化団体であるISO/TC323の活動概要について述べ,2024年5月に発行された(1)ISO 59004「語彙,原則,実装のためのガイダンス」,(2)ISO 59010「ビジネスモデルとバリューネットワークの意向に関するガイダンス」,(3)ISO 59020「循環性パフォーマンスの測定と評価」の三つの規格について,それぞれの概要と発行に至るまでの経緯や各国の動向について解説した。
CEのコンセプトや用語を定義するISO 59004の中で,CEとは「持続可能な開発に貢献しながら,資源の価値を再生,保持,または付加することによって,資源の循環的な流れを維持するための包括的なアプローチを用いる経済システム」と定義されている。市川教授はCEにおけるビジネスのあり方について,従来のバリューチェーンを,共通の目的・戦略・計画に基づくバリューネットワークに変化させていく必要があるとし,バリューネットワークを通じた指数関数的な成長に向けては,適切なガバナンスの実装が重要であると述べた。また取り組みの成果を測る指標については,資源流入側における「流入量の平均再利用率」など,資源流出側における「流出に由来するリユース製品および部品の実使用率」などをそれぞれ必須の指標であるとしたうえで,実際に消費者に理解されやすいのは製品または材料の平均寿命をはじめとした「オプション」と位置づけられる指標であり,必須の指標と同様に重要な役割を果たすであろうと指摘した。
講演の後半では,ISO/TC323にて2025年に日本が新たに提案を予定しているプロジェクト「バリューネットワークの形成に向けたガイダンス」について,KPI(Key Performance Indicator)の提案も含めた概要が紹介された。さらに,今後の日本のめざすべき方向性について,日本の本当のねらいをどこに位置づけるのかが重要であるとして,次のように述べた。
「世界で初めて循環型社会,『サーキュラー』という言葉を使い始めたのは日本でしたが,残念ながらCEという言葉は欧州に定義されてしまいました。欧州勢のねらいは,欧州各国にとってふさわしい産業構造でのCE推進にありますが,日本としてこれをそのまま受け入れることはできません。日本の産業構造にふさわしいCEとは何か,という点は,産業政策として十分に議論しなければならないところです。CEのカギを握るのは,ビジネスにおける高付加価値創出の出口戦略ではないかと考えます。サーキュラーのループにおいて,『再生,破砕・分別,分解・取り出し』という静脈側の取り組みについては,日本でも熱心に行われているところですが,『製造,販売,使用』という動脈側の部分にも力を入れなければ,出口がありません。売れる商品開発のための情報やアイデアを静脈と動脈の両者が共有し,コラボレーションを通じて高付加価値を創出する戦略が求められるでしょう。」
3. 日立-産総研CE連携研究ラボからの講演
続いて,日立-産総研CEラボからの報告として,宮崎 克雅ラボ長による活動概要の紹介のほか,「未来シナリオシミュレータを用いたCE社会の将来シナリオ深耕」,「CE実現に向けた指標のあり方」,「CE型ビジネスへの移行を支援するデジタルソリューションの開発」,そして「国際競争力を強化する日本発のCE国際標準化に向けた取り組み」といったテーマについて,それぞれの研究の概要と成果が共有された。
各講演の内容は,以下のとおりである。
講演1
日立-産総研サーキュラーエコノミー連携研究ラボの活動概要
 宮崎 克雅
宮崎 克雅
産業技術総合研究所 日立-産総研サーキュラーエコノミー連携研究ラボ ラボ長
サステナビリティ研究に関する産総研のグローバルな実績と,日立の先進的なデジタル技術を活用してCEの実現に取り組む日立-産総研CEラボの研究・活動を紹介するにあたり,同ラボの宮崎 克雅ラボ長はCEの実現に向けた課題として次の三点を提示した。
- 資源循環が経済成長につながる社会像の共有
- 環境・経済価値の向上を実現するデジタルソリューションと事例の創出
- 日本が不利益を被ることなく,かつそれぞれの地域性を認め合うルール形成戦略
これらの課題に対応するべく,日立-産総研CEラボでは「グランドデザインの策定」,「デジタルソリューションの開発」,そして「標準化戦略の立案」という三つのテーマを設定し,研究に取り組んでいる。
CEの実現を巡っては各国で法制度や政策の整備が加速する中,資源循環による価値創出に向けたバリューネットワークの重要性が国際的にも認識されつつあり,日本においても関係閣僚会議の設置,循環経済移行のための政策パッケージの策定といった動きが続いている。宮崎ラボ長はCE実現に向けた今後の動きについて,ダイナミックに変化し続ける環境をチャンスと捉えたうえで柔軟に対策を考えていく必要があると指摘し,CPS(Cyber Physical System)を用いて社会課題の解決と経済発展の両立を図るSociety 5.0の時代に向けて,物質,エネルギー,情報・知識という相互に干渉し合う資源の効率的な利用と循環を追求していきたいと述べた。
講演2
未来シナリオシミュレータを用いたCE社会の将来シナリオ深耕
 伴 真秀
伴 真秀
日立製作所 研究開発グループ デザインセンタ UXデザイン部 リーダ主任デザイナー
 森本 由起子
森本 由起子
日立製作所 研究開発グループ デザインセンタ ストラテジックデザイン部 主任研究員
続く講演2では,日立製作所の伴 真秀ならびに森本 由起子から,日立-産総研CEラボの主要な研究テーマの一つである「グランドデザインの策定」に関連して,資源が高度に循環する人間中心の社会の実現に向けた「ありうる将来」と「ありたき将来」を検討する,未来シナリオシミュレーションのねらいと概要が紹介された。
未来シナリオシミュレーションの目的は,これまでの研究の中で導出された「ありうる将来」に至るまでの道筋と,その過程で生じる課題を抽出したうえで,複数の将来シナリオの中から「ありたき将来」を特定することにある。
まず,2万通りに及ぶシナリオを九つのグループに分類し,そこに至るまでの分岐と要因について検討して,最も望ましいシナリオ(行動と循環が一致する仕掛けができている社会)を導出した。さらにその実現に向けてはどのような制度や規制,技術が,いつまでに整備される必要があるのか,有識者とのディスカッションを通じた要件抽出を行い,「ありたき将来」の姿とは「多様な価値観に社会の仕組みが寄り添い,長寿命化による循環を促す社会」であると定義した。
本講演ではその後,「ありたき将来」を具体的にイメージするためのショートビデオが紹介された。今後は,ステークホルダーの動機付けにつながるインセンティブの設計など,引き続きCE実現に向けたロードマップを描き,各種仮説の検証を行っていく。
講演3
CE実現に向けた指標のあり方
 蒲生 昌志
蒲生 昌志
産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 安全科学研究部門 研究部門長
 伊藤 将宏
伊藤 将宏
日立製作所 研究開発グループ 生産・モノづくりイノベーションセンタ グリーンプロセス研究部 主任研究員
産業界における企業団体の活動,製品やサービスなど,CEの実現に向けて多面的な取り組みが広がる中,各国・地域において取り組みの効果や進捗を測るための指標の具体化が進んでいる。講演3ではこうした指標のあり方について,産総研の蒲生 昌志氏および日立製作所の伊藤 将宏が課題意識を共有し,指標の整理・分析の結果を報告した。
社会の「ありたき将来」の実現に向けては,それぞれのステークホルダーが自らの活動に適した指標を選んでいくことが必要である。日立-産総研CEラボでは,指標の選択にあたっては指標間の関係性を意識することが重要であると考え,まず,各種資料から収集した770の指標を分類し,45の基礎指標に集約した。さらにその中から,(1)CE市場規模,(2)バリューチェーン上のGHG(Greenhouse Gas)排出削減量,(3)入口側の再生材利用率,(4)出口側の再生率,(5)最終処分量の五つを「ありたき将来」に寄与する指標として抽出し,これらにひも付く指標の関係性について整理した。検討の結果,これらの指標は相互に作用するものであることが明確となった。各ステークホルダーが指標を選択する際には,以下の三つのポイントが重要である。
- 社会の「ありたき将来」を構成する指標群へのつながりを意識し,複数の指標を確認する。
- 特定の指標を改善する取り組みが,別の指標に対して負の影響を与える可能性があることに留意し,他の指標を用いて影響を確認する。
- バリューネットワーク全体を通じた指標の設定が効果的な場合がある。
講演4
CE型ビジネスへの移行を支援するデジタルソリューションの開発
 河野 一平
河野 一平
産業技術総合研究所 日立-産総研サーキュラーエコノミー連携研究ラボ 特定集中専門研究員
 古川 慈之
古川 慈之
産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 インダストリアルCPS研究センター 研究チーム長
CEの実現に向けては,ステークホルダー間のバリューネットワーク構築を実現するソリューションが求められる。講演4では,産総研の河野 一平氏,ならびに古川 慈之氏が,日立-産総研CEラボが取り組むデジタルソリューションの開発について述べた。
日立-産総研CEラボでは,「適切な循環方法の選択」と「実データに基づく環境負荷の把握」を解決すべき課題に掲げ,これらを解決するためのソリューションの開発を進めている。
それぞれのソリューションの詳細は以下のとおりである。
- 適切な循環方法の選択を支援するライフサイクルシミュレータ
H-AISTライフサイクルシミュレータは,物の流れや業務をモデル化し,CE指標や経済価値を評価するものである。日立グループの事業に本ソリューションを適用したところ,定量的な解析結果に基づいて経済性と環境性を改善する施策の評価・選択が可能であることを確認できた。 - 実データに基づいて環境負荷を把握するための「静脈」のデジタル化
物の循環を担う回収・解体・再生などの「静脈」のデジタル化によってライフサイクル全体の実態を把握するソリューションであり,静脈プロセスにおける工程ごとの原単位作成に向けたデジタル化を推進中である。
日立-産総研CEラボは,これらの二つのソリューションを用いたCPSを通じて,CE型ビジネスの実現に向けたバリューネットワークの構築を牽引していく。
講演5
国際競争力を強化する日本発のCE国際標準化に向けた取り組み
 星野 攻
星野 攻
日立製作所 研究開発グループ 技術戦略室 チーフアーキテクト室 室長
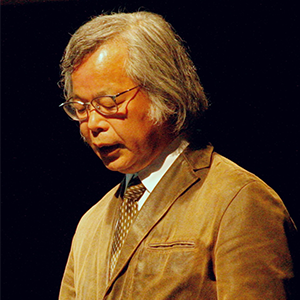 神垣 幸志
神垣 幸志
産業技術総合研究所 企画本部 知財・標準化推進部 標準化推進室 標準化オフィサー
CEでの国際標準化では,製造業にとって不利なルール形成が成される懸念がある。こうした中で日本がグローバルに持続可能な成長を遂げていくためには,国際標準化への積極的な関与・活動が不可欠である。フォーラム前半の最後のセッションとなる講演5では,日立製作所の星野 攻および産総研の神垣 幸志氏が,CE分野の国際標準化における日本の取り組みに関する戦略と,今後の展望について述べた。
日立-産総研CEラボは,国内企業のニーズと課題を踏まえ,(1)CE貢献が生み出す価値を見える化する指標と,(2)残存価値を見える化するグレーディングの標準化活動を推進している。
- CE貢献が生み出す価値の見える化
日立-産総研CEラボが提案する「CE付加価値の生産性」という新指標は,既存の指標と組み合わせることで,再利用・再製造・回収・分別・長寿命化といったさまざまなCE施策を経済性の観点から評価することができる。この指標を活用することにより,大きな付加価値を高効率に生む社会システムや設備への投資を促すことが可能となる。 - 残存価値を見える化するグレーディング
CEにおいては,資源となる製品や材料をむだなく循環させることが求められる。これに対し,動脈側では製品・材料に関する仕様のデータ連携,静脈側では指標などの標準化といった取り組みがそれぞれ進められているものの,動脈―静脈間では製品や材料のデータを効果的に交換できていないのが現状である。
これに対し,先行規格などを活用・整合させながら,評価対象の情報と評価基準に基づいて,客観的にグレードを評価するためのデータモデルの標準化を提案している。
今後は国内外の関係機関とも協力しながら,審議・調整を踏まえ,2026年3月頃までにISO/TC323などへの規格提案を行い,日本発のルール・標準によるイニシアチブを具現化する計画である。
パネルディスカッション
日立-産総研CEラボの活動報告に続いて,(1)CE社会におけるありたき将来と実現に向けた要件,(2)人・企業の行動変容を促すルール,標準化のあり方について,を論点としたパネルディスカッションが開催された。
ディスカッションの前半では,パネリストとして登壇した7名の有識者が自己紹介を兼ねたショートプレゼンテーションを行い,二つの論点に関するそれぞれの認識を共有した。その後,2名のファシリテータによる司会の下,議論が交わされた。
[ファシリテータ]
 増井 慶次郎
増井 慶次郎
産業技術総合研究所 日立-産総研サーキュラーエコノミー連携研究ラボ 副ラボ長
 谷口 伸一
谷口 伸一
日立製作所 研究開発グループ 生産・モノづくりイノベーションセンタ センタ長
[パネリスト]
 長崎 太祐
長崎 太祐
経済産業省 イノベーション・環境局 GXグループ 資源循環経済課 課長補佐
 梅田 靖
梅田 靖
東京大学 人工物工学研究センター 教授
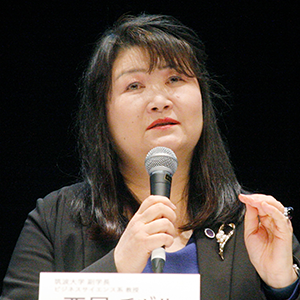 西尾 チヅル
西尾 チヅル
筑波大学 副学長,ビジネスサイエンス系 教授
 細田 衛士
細田 衛士
東海大学 副学長,政治経済学部 教授
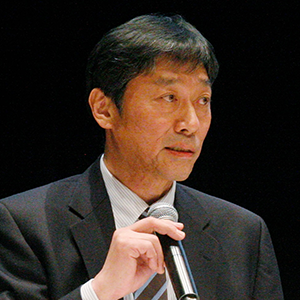 喜多川 和典
喜多川 和典
公益財団法人日本生産性本部 エコ・マネジメント・センター センター長
 清水 孝太郎
清水 孝太郎
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 経済・産業ユニット ユニット長
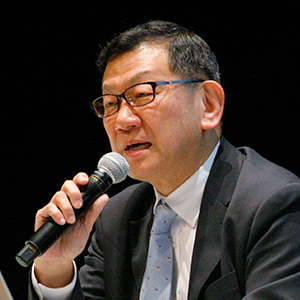 田島 章男
田島 章男
パナソニックホールディングス株式会社 CEエキスパート
論点(1)
CE社会におけるありたき将来と実現に向けた要件
増井本日の発表・報告の中では,バリューネットワークや価値,サービス,ライフサイクル志向といったさまざまなキーワードが出てまいりましたが,そもそもCEはリサイクルとどう異なるとお考えでしょうか。
梅田CEというのは,産業界を筋肉質に変える運動だと思っています。消費者の利便性を向上しながら裏では資源が循環するというのは,一体どのような産業構造なのか,それこそがこのラボで議論すべき課題ではないでしょうか。インセンティブの設計も同様で,その仕組みが機能する裏には何があるのかを常に考えていかなければならないと思います。
細田3R(Reduce, Reuse, Recycle)に比べると,CEは目標が漠然としていて,連携協力も容易ではありません。ですが,元々日本の強みは個人戦より団体戦にあるのです。日本におけるリサイクルがうまくいった背景には,業界における横のつながりがあります。バリューネットワークの構築においてはそういったコクリエイティブな力が重要になるのですが,現状は異業種間での協力には至っていないため,優良な資源が海外へ流出してしまう前に手を打たなければならないと感じています。
長崎経済産業省ではCE推進のドライバーの一つとして,プラスチックなどを大量に使用する業種・業界の方々に,再生材の利用に関する計画を策定してもらい,それをPDCA(Plan, Do, Check, Act)サイクルで拡大していくことを検討しています。例えばプラスチックは再生利用によって質が低下してしまうため,カスケードリサイクルしかできません。これに対して,CEでは,製品間の水平リサイクルを可能な限り追求していくものと考えます。しかし,これを実現するためにはバリューネットワーク全体で協調していく必要がありますので,法改正を通じて再生材の利用義務などを定めることで,動静脈の連携や,製品あるいはリユースモデルの検討のきっかけになればと思っています。
喜多川欧州のCEにおいて製造業が軽視されているのであれば,製造業の強みを生かす日本型のCEをめざしてはと思います。製造業はこれまで,盛んにCEに取り組んできました。なぜなら製造業には生産工場があり,そこでは常に設備の長寿命化が図られてきたからです。製品が流通した先で修理するといっても,製造業の技術がなければ中途半端なメンテナンスで終わってしまいますので,メーカーと製品がつながり続け,長期にわたる使用をサポートする,消費者に寄り添って新しい付加価値を生み出すといった発想があってもいいのではないでしょうか。
増井すると消費者の受容性や,行動変容が気になるところですね。
西尾業界・メーカーの壁を越えた協創の中で,消費者をどう位置づけるのかは重要な問題です。企業が環境に配慮した商品やサービスを提供し,消費者が積極的にそれを購入・使用するというのが理想的な形ではありますが,シェアリングやサブスクリプションといったサービス形態が普及した現在,消費者は目的によって必要な時に必要な物を使い分けることができるようになりました。これは消費者側からすると,非常にマテリアリスティックな状況です。こうした中でどのように消費者をCEのパートナーとして巻き込んでいくかがカギになります。
論点(2)
人・企業の行動変容を促すルール,標準化のあり方について
谷口欧州を中心としてさまざまな国と地域で,CEに関するルールや標準化の議論が行われています。日本が今後どのように動いていくべきか,日本ならではのルールづくりや標準化といった点について,ご意見を伺えますでしょうか。
細田日本人は「個」を強調しません。全体主義的な側面もあるかもしれませんが,一方でそこには,関係性を基調とする確かな強みもあります。モノづくりと異業種の連携も含めて,関係性をベースとした日本人ならではの新しい発想があってもいいのではないでしょうか。例えば規格や標準化の分野においても,欧州や米国に追従するだけでなく,日本らしい文化と伝統を踏まえた規格をこちらから提案していくなど,そこにこそ日本のチャンスがあると考えます。
長崎現在,バリューネットワークのガイドラインを日本として提案しているところですが,関係者間で協調し,ソリューションを共有していくという「日本モデル」を世界に発信していくことが大事だと考えております。また消費者に目を向けてみると,分別収集への協力など,ルールに従う傾向が強いという点でも日本人には強みがあると思います。一人一人の行動がしっかりと資源循環につながっているということを,消費者に分かりやすく伝えていくことも重要なのではないでしょうか。
清水バリューネットワーク,企業の連合体というものにこそ,日本らしさを出せるのではないかと感じます。そこでは「誠実」,「信頼」,「育成」といったような,従来の経営指標である売上や利益では測ることのできない新たな経営指標があると思います。例えば不純物が混ざらないよう,適切にスクラップを売り買いできているかどうか,そういったことを考えるうえではトレーサビリティや規格も必要になるでしょう。また,次の世代につながる人財をいかにして育てていくかも重要です。行動を縛るためのルールを敷く前に,まずは現状への気づきを与える指標の設定や計測といったところに取り組んでいきたいですね。
田島規制するべき点は規制するとして,現状で縛り過ぎている部分を緩和することも大事ではないかと考えています。そのうえで,抑え込むのではなく自発的な行動を促すインセンティブが重要になると思います。バリューネットワークのような,何か新しいことを始めましょうという時に,関係者の理解を得るうえでは制度・法律が拠り所になりますので,ビジネスモデル開発に対しても国としてこれまで以上に支援いただければありがたいです。日本のリサイクル法は,業界別に作られてきましたが,そこに横串を刺す形で再生材の使用に関するルールをつくるなど,CEを加速させる政策によって企業の取り組みも活性化できるのではないでしょうか。その点,製品軸・素材軸の両方で進めていただいている産官学のパートナーシップ,サーキュラーパートナーズでの領域別WG(Working Group)や経産省資源循環経済小委員会での取りまとめも大変期待しているところです。
5. 閉会挨拶
 村山 宣光
村山 宣光
産業技術総合研究所 副理事長 兼 研究開発責任者
 西澤 格
西澤 格
日立製作所 CTO 兼 研究開発グループ長
閉会に際して挨拶に立った産総研の村山 宣光副理事長は,フォーラムの参加者と登壇者に謝辞を述べるとともに,各プログラムの報告・議論を振り返って次のように語った。
「産総研は現在,来年度から始まる第6期中長期計画に向けて研究戦略の再構築を進めております。本日のフォーラムでは,CE社会の実現に向けては価値創造が重要なファクターであるというご意見を頂きましたが,産総研グループとして研究開発と価値づくりを担う体制を整え,CE分野の研究開発についてもこれまで以上に力を入れて,産業界の皆様と共に技術開発および社会実装に取り組んでまいります。」
さらに,日立製作所CTO兼研究開発グループ長の西澤 格は,CE社会の実現に向けたグランドデザインの作成をはじめとする日立-産総研CEラボの研究報告内容に触れつつ,同ラボの今後の活動について述べた。
「日立-産総研CEラボは設立から2年4か月が経過し,CEを巡っては世界中でさまざまな動きが出てきています。3か年計画で始動した本ラボの活動は2025年9月に終了を迎えます。その際,CE社会の実現に向けた『ありたき将来』の姿と,そこに至るロードマップの策定,および開発技術に関する報告書をまとめる予定です。日立においても2025年度からは新たな中期経営計画がスタートします。引き続き本活動を通じて,CE社会の実現に貢献していきます。」




