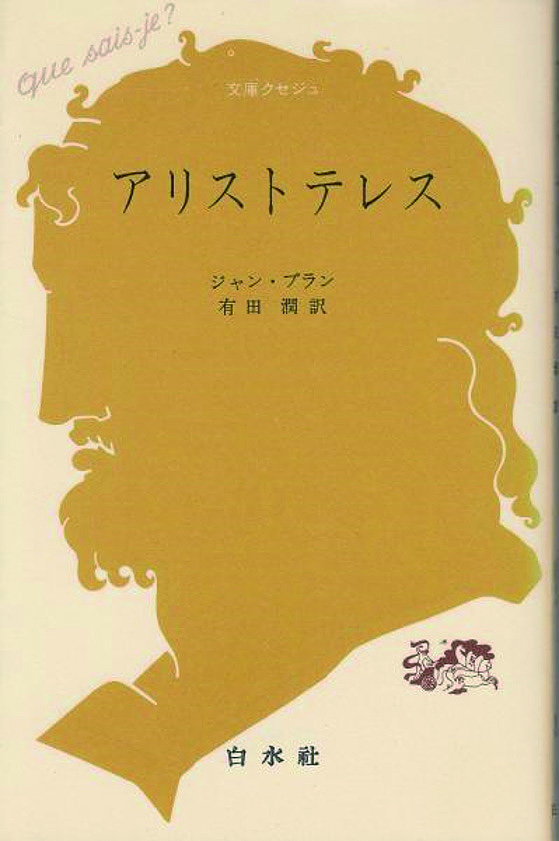Innovators’ Legacy:先駆者たちの英知科学・技術史から探るイノベーションの萌芽[第4章]イスラム科学技術概説(Part1)
1.イスラム科学はミッシングリンク
一般的に科学といえば,ユークリッドの幾何学,ヒポクラテスの医学,あるいはデモクリトスの原子論など,古代ギリシャを思い浮べるだろう。その次はといえば,ガリレオ,ケプラー,ニュートンなど17世紀のヨーロッパ人の名前が浮かぶだろう。この間,実に1,500年もの長い空白時間があるにもかかわらず,ヨーロッパの科学者の名前は誰一人として挙がらない。これは何も読者の皆さんが不勉強であるからでなく,日本や欧米の大多数の人々の共通認識がそうなのである。しかし,イスラムから見るとまったく違った風景が見える。結論からいうと,この間,西洋の科学はヨーロッパを去り,イスラム圏で発展した。科学を欧米視点で見るかぎり,紀元2世紀から千数百年間はリンクが切れた状態,つまりミッシングリンクになっているのだ。イスラム圏を含めて考えることでようやく一連のつながりが見えてくる。
科学はヨーロッパの専売特許だとの認識からでは科学の発展は理解できない。本論では,科学のミッシングリンクであるイスラム科学を理解するうえで必須となる,古代ギリシャの哲学者・アリストテレスに絞って説明する。
科学は哲学とどういう観点で関連するのか,と不思議に思うだろう。その疑問はもっともで,私も日本人が書いたイスラム関連の本を随分多く読んだが,この点について明確な答えを得ることができなかった。しかし,イラン人のナスルの書いた『イスラームの哲学者たち』でようやく答えを見つけることができた。ポイントを要約すると以下のようになる。
「イスラムでは,科学は哲学の一部として考えられた。中世以降のヨーロッパでは哲学と科学を分離してそれぞれを探求したが,イスラムでは文化人は両方とも区別せずに探求した。」
この点を理解すると,なぜイスラム科学の話にギリシャ哲学が出てくるのか,それも,なぜプラトンではなくアリストテレスなのかが分かる。本稿ではこの点を明らかにしたい[以下,イスラムは宗教とともにイスラム教徒(ムスリム)の両方の意味で用いる]。
2.ヨーロッパ人のイスラム世界へのあこがれ
図1|グラナダのアルハンブラ宮殿  出典: https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/histoire-al-andalus-decouverte-espagne-musulmane-13408/
出典: https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/histoire-al-andalus-decouverte-espagne-musulmane-13408/
科学がヨーロッパの専売特許だとの誤解と同様に,「先進的なヨーロッパ,遅れているイスラム」という誤った図式も広く信じられている。さらにキリスト教とイスラムの対立も,2001年の9.11事件(アメリカの同時多発テロ)以降,イスラム国やアフガニスタンのタリバン政権樹立などで,一層激しさを増している。その中で,イスラムは貧しいがゆえに欧米を敵と見なしていると考える風潮が強まっているが,歴史を振り返るとその逆の時代の方がずっと長かったということが分かる。長い間,ヨーロッパ人はずっとイスラムにあこがれ続けた。この点は例えばフランスの歴史家,フェルナン・ブローデルの著書に見ることができる。ブローデルは歴史の視点を政治史中心から生活史中心に変えた「アナール派」の領袖として,大きな影響を与えた。代表作に『地中海』や『物質文明と資本主義』があるが,いずれも膨大な資料を駆使して,人々の生活実態を目に見えるように描き出している。私は『物質文明と資本主義』をまだ4分の1程度しか読んでいないが,誇張ではなくそれこそ毎ページに新しい発見があるといってよい。私はこの本からヨーロッパ人は長らくイスラムの洗練された高い生活水準にあこがれていたことを再確認した。このあこがれが結果的に16世紀にヨーロッパがアフリカの南端を回ってアジアに進出する原動力となった。現在,オイルマネーを除くとヨーロッパは富と政治力においてはイスラム諸国に対して格段の優位に立ってはいるが,これは有史以来の歴史においては例外に属するような事象である。もっとも,ヨーロッパとアラブは必ずしも対立していたのでもなく,政治,経済だけでなく,文化的にも非常に密接な関係にあったし,今もある。ヨーロッパとアラブの関係を正しく理解するには,中世における両者の哲学・科学を中心とした文化交流を知っておく必要がある。
なお,ブローデルと同じくヨーロッパ人であるモンゴメリ・ワットの『地中海世界のイスラム』およびジクリト・フンケの『アラビア文化の遺産』にもイスラム文化に対するヨーロッパ人の強いあこがれを見ることができる(もっとも,両人とも心情的にかなりイスラムびいきではあるが)。
3.呼称の問題―アラブあるいはイスラム?
ところで,今回取り上げるのはアラブ・イスラムの科学と技術であるが,アラブ(アラビア)とイスラムの両方の修飾語がある。世の中にはどちらの言葉も使われているので,紛らわしい。その理由を説明しよう。まず,イスラム教というのはご存じのようにムハンマドが創始した宗教であるので,イスラムの科学技術というとイスラム教徒が発展させたという意味になるが,実際には,イスラム教徒以外の宗派の人間,具体的にはキリスト教徒,ユダヤ,ペルシャ,トルコなどが多く貢献している。一方,アラブというのは,本来は現在の国名でいうサウジアラビア土着のセム族を指す。しかし,その後,イスラムが中東,北アフリカなどに拡大するにつれて,他の部族も「アラビア語を話す」という意味でアラブと呼ばれるようになった。それで,アラブの科学技術という時は「アラビア語を話す人たちによって発展させられた科学技術」となる。ところが,この地域の科学技術の発展にはアラビア語以外の言語,具体的にはシリア語,ヘブライ語,ペルシャ語なども使われている。それゆえ,「アラブの科学技術」といっても「イスラムの科学技術」といっても,どちらも「帯に短し,襷に長し」である。今回は便宜的に「イスラムの科学技術」と呼ぶことにする。
4.イスラム社会の発展
イスラムは誕生してからわずか数十年でアラビア半島はいうまでもなく,東はペルシャ,西はエジプト,リビア,北はカスピ海まで広まった。この地域の人々はそれ以前から,発達した交通網を介して相互に交流していた。人種的には異なっていたにしろ,乾燥した地中海性気候で,麦作と牧畜という生活環境が近いので,イスラム教徒に支配されても違和感をさほど感じなかった。また宗教的観点からは,ペルシャで信仰されていたゾロアスター教は一神教に近い考え方なので,イスラムの一神教には抵抗が少なかった。文化面ではエジプトと地中海東岸(レヴァント)では,アブラハム,ノア,アダムなど旧約聖書に現れる伝説上の人物にまつわる神話を共有していたし,言語面ではこの地域で使われていたヘブライ語やアラム語はアラビア語と同じくセム語族に属する言語である。結局,イスラムはアラビア語を主要言語とし,すべての人が土着の言葉を捨てたわけではないものの,アラビア語がイスラム圏の共通語となった。
さて,イスラム教徒が制圧したシリア,メソポタミア,ペルシャ,エジプトなどの地域はムハンマドの故郷であるアラビア半島のベドウィンの生存圏と比べるとはるかに文化的先進地域であった。ベドウィンは交易を主業としていた商人であり,技術はともかくも科学に対してまったく関心を持たなかった。イスラム教徒の最初の政権であるウマイヤ朝はベドウィンのアラビア人を優先する政治体制をつくり,科学に対する無関心の伝統を引き継いだ。
ウマイヤ朝を倒したアッバース朝は,ヘレニズム文明の教養を身に着けたペルシャ人に支持されて政権を樹立したため,人種による差別はなく,ペルシャ人が保持していたギリシャ文明,その中でも主に哲学と自然科学を積極的に取り入れた。それだけでなく,アッバース朝の最初のカリフたちはペルシャ人の臣下やブレーンたちの影響を受けて,揃いも揃ってヘレニズム文明の愛好家であった。このとき初めて,イスラムは外来の学問として,哲学,論理学,医学,薬学,天文学,数学,化学,錬金術を受け入れた。逆に言うと,アラブ土着の学問にはこれらの分野が欠落していたということになる。
さて,イスラムは一神教としては,ユダヤ教,キリスト教から数百年以上も遅れて最後に成立したため,これらの宗教と比較して神学理論がないに等しく,イスラムを征服地に普及させるうえでも,神学理論を確立することが急務となった。このとき,伝統的な学問では不足であった。ナスル著の『イスラームの哲学者たち』にはアッバース朝のカリフたちがギリシャ文献の翻訳に惜しみない支援をした理由を次のように説明する。
「ウマイヤ朝時代,ユダヤ教やキリスト教側からイスラムの教義が論駁(攻撃)されたが,その時に彼ら(ユダヤ教徒,キリスト教徒)が援用したアリストテレスの論理や哲学を,ムスリムは知識がなかったため理解できず,やりこめられた。アッバース朝のカリフたちはイスラムの名誉のために,自分たちもアリストテレスの論理と哲学を身につけて,こういう事態を打破すべきと考えた。」
5.アリストテレスを我が物としたイスラム
イスラムが熱心にアリストテレスを理解しようと努めるようになったのは,第一義的にはユダヤ教徒やキリスト教徒との宗教論争に勝つためであったが,それだけにとどまらなかった。前述したように哲学と科学とを区別せず,真理を探求するイスラムの文化人にとって,アリストテレスの宇宙論(地球は宇宙の中心にあり不動)や目的論的自然観(自然界のものは所期の目的があって作られている)は思考の原点ともいえる。アリストテレスについて論じ始めると「イスラムの科学」という限定された話だけでは収まらず,ギリシャ哲学やキリスト教,イスラム教,さらには,中世ヨーロッパのスコラ哲学まで間口の大変広い話になってしまうので,ここではイスラムでアリストテレスが必要とされた理由について述べるにとどめたい。
6.私がなぜアリストテレスに興味を持ったか
図2|アリストテレスの胸像  出典: https://m.naftemporiki.gr/story/1105941/epeteiako-etos-aristoteli-ta-elta-timoun-ton-megalo-ellina-filosofo
出典: https://m.naftemporiki.gr/story/1105941/epeteiako-etos-aristoteli-ta-elta-timoun-ton-megalo-ellina-filosofo
まず,私がアリストテレスを重要だと感じたきっかけから話を始めよう。第1章Part 2の中で,私がタトンの本を見て「あの砂漠に科学?」と驚いたことを述べたが,イスラムに本当に科学があったのか,まだ半信半疑のままであった。しばらくして,私が勤めている会社に一人の技術者が部長職で転職してきた。彼は技術者として一流だったが,ある時,雑談の中で彼がアリストテレスの信奉者ということを知り驚いた。私自身はさておき,まさか技術者でありながらギリシャ哲学にのめりこんでいる人を間近に見るとは思ってもみなかった。話の中で「アリストテレスの注釈の中にはアラビア語で書かれたものが多い」との彼の一言に,それまで私の頭の中に巣食っていた「イスラム―科学」というつながりが,「イスラム―科学―アリストテレス」というさらに謎めいたリンクに変わった。しかし,この時はまだアリストテレスに対してさほど興味は掻き立てられなかった。というのは第2章Part 2で述べたように,私はそれまでに『ニコマコス倫理学』,『形而上学』,『政治学』,『弁論術』,『動物誌』などアリストテレスの本を読んでいて,退屈な話しぶりをする人物だという印象が強く残っていたからである。
さて,その後2008年に京都大学に奉職するようになり,念願であったリベラルアーツ教育を行うことができた。教養科目の一つとして『国際人のグローバルリテラシー』という科目を開講した。ギリシャ・ローマ,イスラム,中国,朝鮮(韓国),東南アジア,日本など多くの文化圏の話をするのだが,ギリシャの哲学について講義をするにあたって,はたとアリストテレスは未読のものがかなりあることを思い出した。都合のよいことに,アメリカ留学中にアリストテレスのローブ古典叢書を全巻買い揃えてあったので,早速これを読むことにした。一年ばかり掛けて,アリストテレスの主要著作をほぼ読み終えたが,率直に言ってアリストテレスのどこが凄いのか分からないだけでなく,肝心の「イスラムがなぜアリストテレスを必要としたか」に関しては手がかりすらつかめなかった。
7.アリストテレス理解に導いてくれた2冊の本
ローブのアリストテレスと並行して日本の哲学者の書いたアリストテレスの解説本をいくつか読んではみたものの,私の疑問に応えてくれる本はなかった。しかし,イギリス人・ロイドの『アリストテレス その思想と成長』とフランス人・ジャン・ブラン『アリストテレス』を読み,すっかり疑問が解決した。これらの本の特徴は,いずれもアリストテレスがイスラムと中世ヨーロッパに与えた影響を哲学の観点だけでなく,科学の観点から解説していることである。というのは,日本のアリストテレス学者は,大抵の場合,形而上学的観点からの説明に終始し,アリストテレスの科学書にはほとんど触れていない。さらに,日本人には縁遠いキリスト教という観点からアリストテレス哲学が中世のスコラ哲学にどのような影響を与えたのかという点に関しても私を納得させてくれる説明は見当たらなかった。ところが,これらの本,とりわけブランの本は私の疑問の核心にズバリ切り込んで,明確に答えを示してくれた。結論だけをいうと,アリストテレスの「物は誰かによって動かされない限り動かない」という前提から,「物が運動するには運動の連鎖が存在しなければいけない」と考えた。そして運動の連鎖のトップバッターを「第一動者」と呼び,「第一動者」だけは他者から動かされない者,すなわち「不動の動者」であるとした。この「不動の動者」をアラブの哲学者たち,そして後にヨーロッパの哲学者たちが自分たちの信じる宗教の神に置き換えることで,アリストテレスの論理がそのまま流用できることに喜んだ。
さらに,アリストテレスは自然界を観察して,生物は必ず同種の子どもを生むし,石は必ず落下するのに火は必ず上昇するなど,すべての現象には規則性と秩序が備わっていることを見て「不動の動者」は自分の意図を実現するためにこういった規則性と秩序を与えたと考えた。また,多くの動物の観察から,動物の体の各部には必ずある目的を達成するために必要十分な機能が備わっているという目的論的自然観を唱えた。さらに,この考えを推し進め,羊がふさふさとした羊毛を蓄えるのは人間がそれから暖かい着物を作るためという人間中心の目的論的思考に到達した。この点がイスラムやキリスト教の考える神の概念と合致したので,アラブやヨーロッパの信者たちがこぞってアリストテレスを研究した。結局,「不動の動者」という概念は単に自然学だけでなく,存在論や神学論にまで及ぶことになり,アラブにおいて,また中世ヨーロッパにおいて,アリストテレス哲学が神学理論を構築するうえで必須の基盤となったのである。
ついでに言えば,アリストテレスは8世紀,9世紀に一度イスラムに浸透したあと,ヨーロッパの12世紀ルネッサンスで,アラビア語からラテン語へ翻訳されて広まった。つまり,アラブがアリストテレスを取り入れたところで話が終わるのではなく,ヨーロッパがアラブからアリストテレスを逆輸入するまでが一連の流れなのである。とりわけ,この後半の過程でアリストテレス哲学を縦横無尽に引用して,壮大なキリスト教神学理論を確立したのが,トマス・アクィナスであった。
結局,アリストテレスは,死後しばらくの間はプラトンの威光の影に埋もれて原稿はまともに編纂されず,紀元前1世紀になって,打ち捨てられていた草稿がようやく整理された。その後,西ローマ帝国では論理学など一部の著書がラテン語に翻訳された程度で,アリストテレスといえば論理学者としてのみ知られていた。一方東ローマ帝国の知的財産を引き継いだイスラムでは,論理学だけでなく,哲学と自然科学も含め,全集が幾度となくアラビア語に翻訳され,イスラムの文化人たちの思想の根幹を成した。その後,12世紀以降,アラビア語のアリストテレス著作がラテン語に翻訳されて,ヨーロッパ人は初めてアリストテレスの全体像を知ることができた。次回説明するように,イスラム科学にはこのようなアリストテレスを巡る議論が必ずつきまとう。
8.頭の中が「疑問のゴミ屋敷」
今回もそうだが,なぜ私が自分の経験を披露するかと言えば,現在の一般的な教育のあり方,あるいは知識獲得の方法について大いに疑問を感じているからである。日本の教育は突き詰めれば大学受験で勝者になるための効率的学習法を訓練している。このシステムでは,覚えるべきことを短期間に,少しでも多く覚えることが良しとされる。たとえ,覚えるべき内容に疑問を感じたり,さらに深く知りたいと好奇心が出てきたりしても,横道に逸れることは時間の浪費だとして,推奨されない。こういったシステムに小学校以来,十数年慣れてしまうと,自分に関心のあるテーマを見つける気力・気概が萎え切ってしまう。
私は社会人にとって「疑問を持ち,それを解決するために読書し,考える」ということが非常に重要だと考えている。通常,疑問を感じると解決したい強い欲求が湧いてくるものだが,残念なことに,日常の忙しさにかまけて「まあ,いいか,知らなくたって別に損するわけでもないし……」と考えているうちに疑問はしぼんでしまう。こうなっては非常にもったいない。疑問はいつまでも後生大事に頭の中にしまっておかないといけないのだ。次々と疑問が溜まり,頭の中がいわば「疑問のゴミ屋敷」状態になるのが,社会人として視野を広めるには必須の心構えである(ありがたいことに,頭の中が「疑問のゴミ屋敷」になったところで誰にも迷惑はかからない!)。反対に,疑問がその内にしぼんでしまう人は,自分の生活に直結しないような事柄に対する感受性が次第に薄れていく。そして,ついには無反応,無感動な人になってしまう。そうならないように,疑問は解けないかぎり手放してはいけない。ずうっと疑問を抱えていると,不思議なことに,必ずといっていいほど疑問を解くヒントを与えてくれる本に巡りあうことができる(今回の例では,ブランの『アリストテレス』がそうだ)。疑問をすぐに手放してしまう人,諦めの早い人に,女神は微笑まない。
参考文献など
- [71]
- 『イスラームの哲学者たち』,S.H.ナスル(黒田寿郎,柏木英彦・訳),岩波書店(1975)
イスラム社会における哲学者3人,アヴィセンナ(イブン・シーナ),スフラワルディー,イブン・アラビーについて説明している。紙面の都合もあろうが,著名な2人の哲学者,アル・ガザーリーとアヴェロエス(イブン・ルシッド)にはほとんど言及されていないのは残念だ。著者のナスルはイラン人であるので,イスラムの視点からギリシャ哲学,とりわけアリストテレスをイスラムが必要とした理由を明確に示してくれている。 - [72]
- 『物質文明・経済・資本主義』,フェルナン・ブローデル(村上光彦・訳),みすず書房(1986)
本文参照。 - [73]
- 『アラビア文化の遺産』,ジクリト・フンケ(高尾利数・訳),みすず書房(1982)
著者のフンケはアラビア人がヨーロッパ文化に対して及ぼした影響についてヨーロッパ人があまりにも無知であることを是正する必要があると強く感じていたようだ。客観的な立場で,アラビア人の文化のヨーロッパへの流入について,実に多岐にわたり説明する。スペインとシチリアを経由した文化流入について具体的な例を挙げて説明する。とりわけ,天文学と医学に関しては詳細な説明がある。例えば,P.134では,ガレノスの血液循環理論の間違いをハーヴィが正したという一般的な認識に対し,実は400年も前にアラビアの医師が発見していたと指摘している。 - [74]
- 『地中海世界のイスラム―ヨーロッパとの出会い』,モンゴメリ・ワット(三木亘・訳),筑摩書房(2008)
フンケと同じく,ヨーロッパ人のイスラムに対する偏見,蔑視に批判的な見地に立つ。コレージュ・ド・フランスでの連続講義をまとめたものとはいいながら,小冊子にしては非常に盛り沢山の内容があり,記述も示唆に富む。中世ヨーロッパがイスラムの先進性にいかに強くあこがれていたかがよく分かる。
基本的に科学はヨーロッパのものという強い偏見がヨーロッパ人(広くは欧米人)の中にある。科学史の研究書や出版物の多くは欧米人が書いているので,イスラム科学を軽視している。モンゴメリ・ワットやフンケのように,公平な(あるいは,いささかイスラムびいきの)立場からの発言は貴重である。P.164~166にヨーロッパ人のイスラムに対する劣等感と,その裏返しとしてギリシャ・ローマの科学を持ち上げる心情がかなり赤裸々に,そして批判的に書かれている。 - [75]
- 『アリストテレス その思想と成長』,G.E.R.ロイド(川田殖・訳),みすず書房(1973)
ロイドが本書を出版したのは,35歳の時であるが,内容は日本の碩学ですら及びもつかないほど広く深いものである。それも単に,学説を羅列するのではなく,種々の著作からアリストテレスの思想の全体像を見せてくれる。
その中で,彼はアリストテレス研究の意義を次のように述べている。
「彼の自然学的著作はもはや自然科学を学ぶ者にとっての出発点ではない。しかし彼の業績について知識を持つことは,十七世紀に始まる近代科学の根源を理解するためには必須の前提条件である。」
つまり,17世紀以降の近代科学はアリストテレスの間違った理論を実験的手法で照明することで発展を遂げたという趣旨である。さらにロイドはアリストテレスを自然科学や哲学という限定した関心分野からだけでなく,人間知性の働きに関心を持つあらゆる人々にとって,その力の広がりと独創性ゆえに依然として最も興味津々たる,かつ最も取り組みがいのある研究題目たることを失わないであろう,と断言する。 - [76]
- 『アリストテレス』,ジャン・ブラン(有田潤・訳),白水社(1962)
私はアリストテレスの解説書をかなり読んだが,なぜアリストテレスがまずはイスラムで,次いで中世ヨーロッパで熱狂的に支持されたのかの根本理由が分からなかった。というのは日本人の書いた解説書はアリストテレス哲学,とりわけ『形而上学』からの引用とその解説で,ページが埋まっていたからである。しかし,このブランの本は違った。アリストテレスの哲学関連の書物だけでなく,自然科学の本に関しても幅広く触れ,さらにはキリスト教の神学理論構築の観点にも言及している。「第4章 自然学」を読んで,私は初めてイスラムやヨーロッパの神学者がアリストテレスの論理を必要とした理由に納得できた。日本人哲学者のアリストテレス理解との隔絶した違いは同じ「自然学」というテーマで,例えば今道友信『アリストテレス(講談社学術文庫)』と比較するとよく分かる。 - [77]
- 『イスラームからみた「世界史」』,タミム・アンサーリー(小沢千重子・訳),紀伊國屋書店(2011)
本書の一節に,イスラムがアリストテレス以外のギリシャ哲学,具体的には新プラトン主義にも自分たちの教義を正統化する根拠を見いだしたという文句が以下のように見える。
「イスラムがアレクサンドリアを征服した時,新プラトン主義者のプロティノスを発見した。宇宙の万物は一つの有機体のように互いに結びついており,それらすべてが統一されて単一の神的存在たる『一者』を構成し,この一者から万物が流出し,万物はやがて『一者』に帰還する,とプロティノスは説く。ムスリムはこの『一者』にムハンマドが唱えたアラーの唯一性に関して唱えた終末論的世界観に通ずるものを見いだして興奮を覚えた。」
もっとも,このようなギリシャ哲学に喜んだムスリムというのは,本来のアラブ,つまり遊牧民のベドウィンではなく,かつてギリシャ文明が浸透した地域に住んでいた知識人と推定される。 - [78]
- 『十二世紀ルネサンス』,伊東俊太郎,講談社(2006)
本書の主テーマは12世紀のヨーロッパに興ったルネッサンス(文化革命)であるが,科学史の観点からギリシャ科学・哲学がイスラムに伝わった経緯と,その逆流,つまりイスラムからヨーロッパにイスラム科学が伝わった経緯の両方がしっかりと書かれている。同著者(伊東氏)の『近代科学の源流』と合わせて読むとよい。 - [79]
- 『中世の覚醒』,リチャード・ルーベンスタイン(小沢千重子・訳)紀伊國屋書店,(2008)
本題は「イスラム世界で受け継がれてきたアリストテレスが12世紀にアラビア語からラテン語に翻訳されることで,中世ヨーロッパが終焉した」という意味である。中世ヨーロッパが主テーマでありながら,イスラムの役割も公平に評価している。結局,中世ヨーロッパの文化人たちがアリストテレスを求めたのは,イスラム同様,宗教論争に打ち勝つための論理の精緻化と知識の拡充であったことが分かる。